『総務』が『採用』を兼ねていませんか? 地方企業が採用で勝つための「攻める人事部」のつくり方
「日々の勤怠管理や給与計算に追われながら、ハローワークへの求人票を出し、時には社員の愚痴を聞き、入退社の手続きもこなす…。」
地域の企業、特に中小企業では、総務・庶務担当者が事実上「人事のすべて」を担っているケースが少なくありません。長年にわたり、その体制で会社を支えてこられたことでしょう。
しかし、深刻な人材不足が社会問題となり、「人的資本経営(=人を”資源”ではなく”資本”と捉え、投資し、価値を最大化する)」という考え方が広まる現代において、従来の「総務兼任」体制のままでは、企業の成長に必要な「人材」という最も重要な経営資源を活かしきれない事態に陥っています。
本記事では、今最も見直すべきテーマである「採用」「人事」「労務」の3つの役割を整理します。そして、なぜ今その見直しが「会社の売上を上げるため」に必要なのか、さらに限られた人員でどう機能を分業し、戦略的に「連携」させていくべきか、その具体的な進め方を解説します。
目次
なぜ今、「総務が全部やる」体制を見直すべきなのか?
「うちは昔からこのやり方で回っているから大丈夫」 そう考える経営者や担当者の方も多いかもしれません。しかし、時代は「人事」に求める役割を大きく変化させました。「なんとなく」の人事管理が通用しなくなった背景には、明確な3つの変化があります。
背景1: 「採用」は”守り”から”攻め”の経営戦略へ
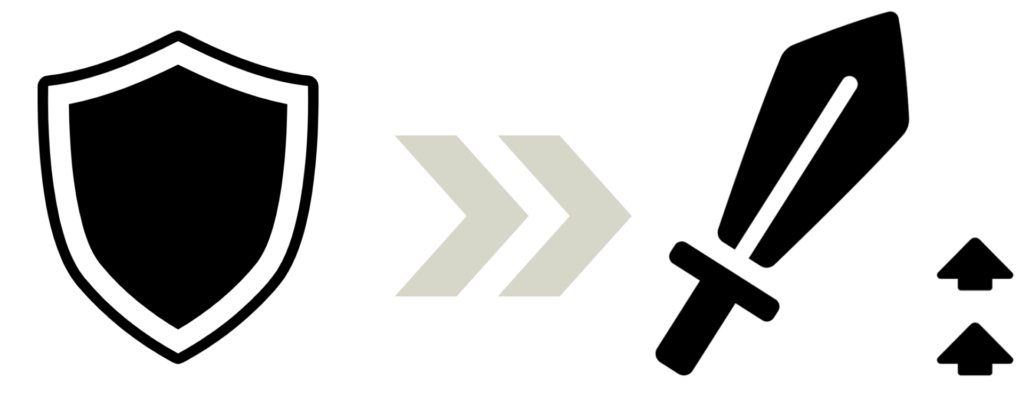
かつての採用は、退職者が出た際の「欠員補充」(守り)が中心でした。しかし今は違います。事業を成長させるため、新しい価値を生み出すために、戦略的に「仲間を集める」(攻め)活動こそが採用です。
地域の企業であっても、求職者は全国の企業と待遇や働きがいを比較検討しています。「総務の兼務」で出した求人票では、数多ある競合企業に「選ばれる」存在にはなれません。採用は、未来の売上を創るための「投資活動」であるという意識改革が急務です。
背景2: 「人事」は”管理”から”価値創造”へ
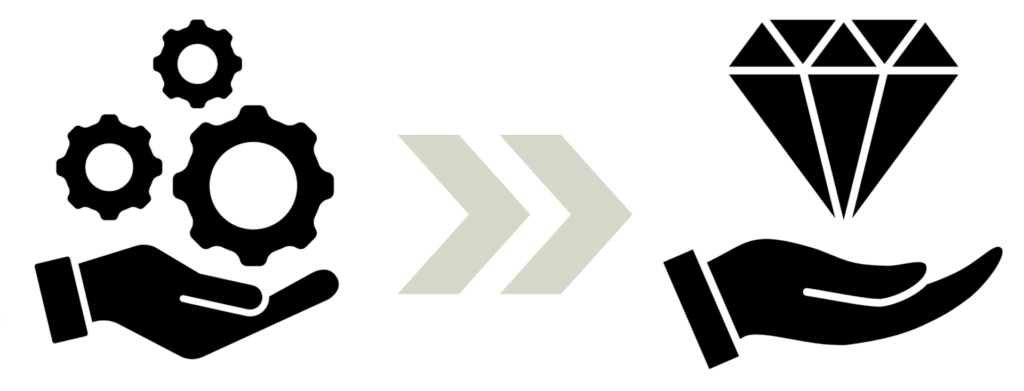
限られた人材で成果を出すためには、個々の能力を最大限に引き出す必要があります。入社した社員をただ「管理」するだけでは、成長は望めません。
「人を活かす」ための仕組み、すなわち公正な評価制度、スキルアップを促す育成体系、そして個々の強みを活かす戦略的な配置(=人事)がなければ、せっかく採用した貴重な人材も定着せず、その能力は宝の持ち腐れとなってしまいます。
背景3: 「労務」は”義務”から”魅力”へ

法令を遵守した給与計算や勤怠管理(コンプライアンス)は、もはや「やって当たり前」の最低ラインです。
現代の求職者や従業員は、「働きやすさ」をシビアに見ています。柔軟な勤怠管理、安心できる就業規則、積極的なメンタルヘルスケアといった「労務」の整備は、今や採用ブランディングの一環であり、人材が安心して長く働くための「土台」そのものなのです。
これらの変革を、「担当者の気合い」や「個人のスキル」だけで乗り切ることには限界があります。だからこそ、経営者が意識的に「役割」を分け、効率的に業務を進める「仕組み」を作ることが不可欠なのです。
その業務、”攻め”ですか?”守り”ですか?「採用・人事・労務」役割と適性
では、具体的に3つの役割はどう違うのでしょうか。ここで明確に整理します。 この3つの仕事は、それぞれが「全く別の専門職」であり、求められるマインドセット(心の持ち方)や適性が異なります。
役割1:労務(守り・土台)
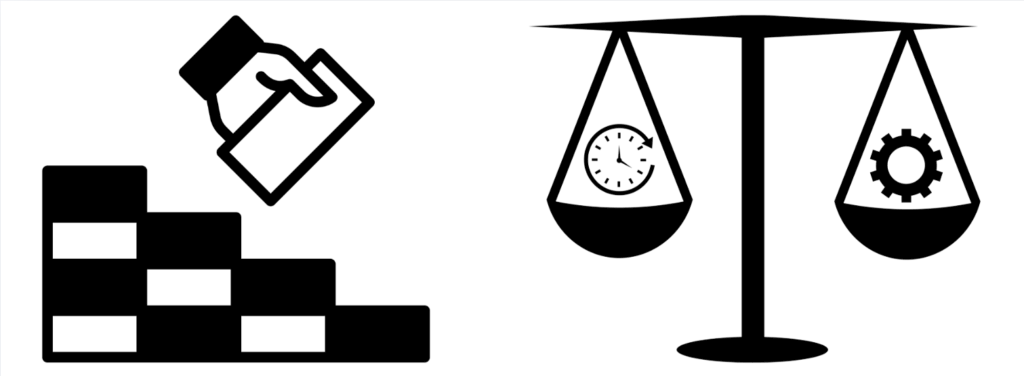
労務の主な仕事は、「会社と社員の生活を”守る”こと」です。 給与計算、社会保険の手続き、勤怠管理、就業規則の整備、入退社手続き、安全衛生管理などがこれにあたります。
仕事の進め方や求められる適性は、「正確さ」「堅実さ」「公平さ」です。1円の計算ミスも許されず、法律を守り、社内のルールを公平に運用することが求められます。 また、社員のプライベートな情報(給与、病歴、家庭の事情など)を扱うため、信頼して相談できる「口の堅さ」も絶対に必要です。社員が安心して働ける土台を作る、非常に重要な役割です。
役割2:採用(攻め・未来)
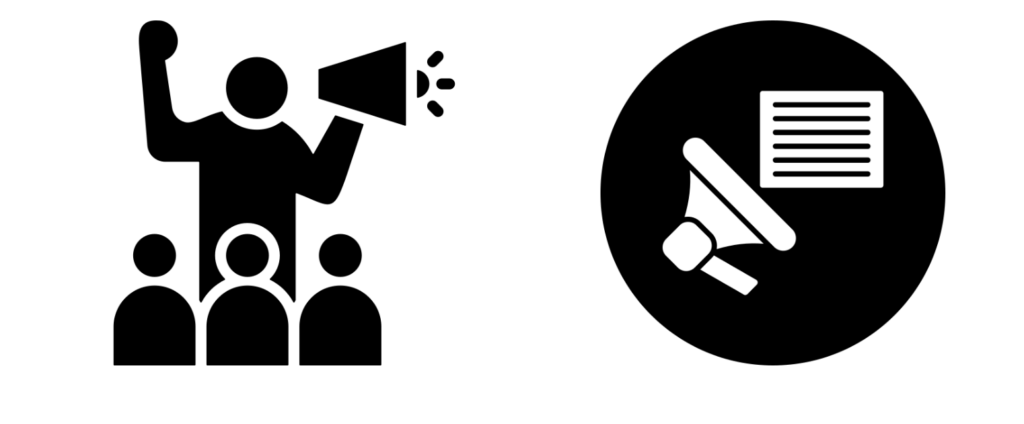
一方、「採用」の仕事は、「会社の”未来を創る”こと」です。 会社の魅力を外部に発信する(SNS、ブログ、説明会など)、スカウトを送る、候補者と会い会社のビジョンを語り口説く、といった活動です。
これは、やっていること自体が「営業」や「マーケティング(広報活動)」と非常に近いのです。 求められる適性は、労務とは正反対です。「まずやってみよう」「ダメなら変えよう」というスピード感や、新しい挑戦を恐れない柔軟性が求められます。
「攻めの採用」で成果を出せる人には、主に4つのタイプがあります。
①市場理解のプロ(=客観的な”モノサシ”を持つ人)
これは、人材紹介会社(転職エージェント)の営業経験者などが典型です。 彼らの最大の強みは、「N数(=採用活動経験数)」、つまり「転職希望者」と「求人企業」に触れてきた絶対量が多いことです。 何百人という転職者と面談し、何十社という企業の求人票を理解してきた経験から、社内の常識ではない「客観的な相場観(モノサシ)」を持っています。
「この経験を持つ人は、市場全体で今これくらいしかいない」
「他社は、このポジションの人にこのくらいの給与水準を出している」
「ウチの会社のこの条件は、他社と比べて魅力的だが、ここは弱い」
こうした相場観が分かるため、「なんとなく」ではなく、データと経験に基づいて「どうすれば採用市場で勝てるか」の戦略を立てることができます。
②交渉・魅力付けのプロ(=”売る”力、”口説く”力がある人)
これは、社内でトップクラスの成果を出してきた「営業」や「マーケティング」の担当者です。 採用は「営業活動」そのものです。
「営業」で成果を出せる人は、「相手(候補者)が何を求めているか、何に不安を感じているか」を察知し、自社の魅力を「相手に合わせて」伝え、不安を解消し、決断を後押しする「口説く力」に長けています。
「マーケティング」で成果を出せる人は、「どう見せるか」のプロです。求人票のキャッチコピー、SNSでの発信、会社説明会の資料作りなど、まだ自社を知らない人に「響く」メッセージを設計し、届ける「魅力化」のスキルを持っています。
③現場のエース(=”リアル”を語り、”巻き込む”力がある人)
これは、現場のマネージャーや、社内でイキイキと活躍しているエース社員のことです。 候補者が面接で一番知りたいのは、「実際に働く人」の「リアル」な話です。このタイプが採用に関わると、仕事の「楽しさ」も「大変さ」も自分の言葉で具体的に語れるため、その話に「信頼感」が生まれます。
また、採用は人事だけで完結するものではなく、現場の協力が不可欠です。「自分たちの仲間探し」という当事者意識を最も強く持ち、他部署を巻き込む「求心力」がある現場のエースは、最強の採用担当になり得ます。
④ファン作りのプロ(=”物語”を発信できる人)
これは、広報・PR担当者や、個人のSNS・ブログ発信などが得意な社員です。 現代の採用は、「給与」や「待遇」といった「条件」だけの競争ではありません。
特に地方企業や中小企業は、「社長の理念への共感」「働く人の雰囲気」「会社の社会的な意義」といった「情緒的な価値」で選ばれることが増えています。 このタイプは、会社の日常や理念を「物語」として発信し、入社前から会社の「ファン」を作る力があります。
役割3:人事(戦略・育成)
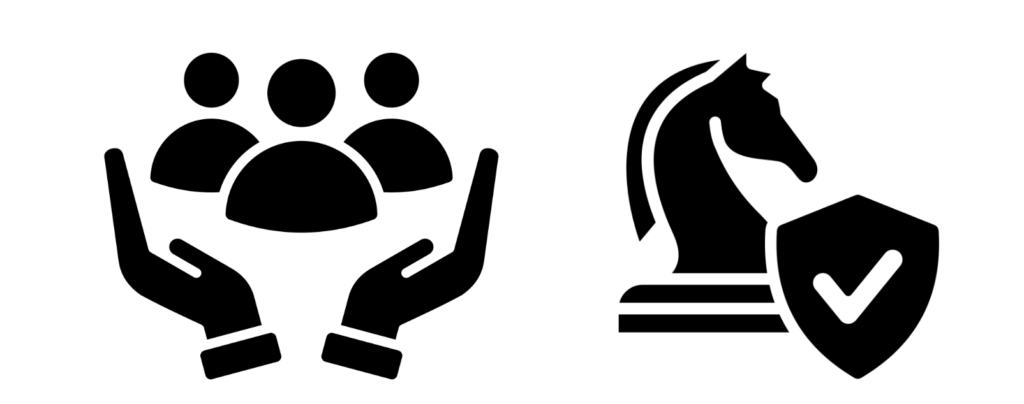
そして「人事」の仕事は、「社員の能力を最大化し、組織を強くする」ことです。 経営戦略に基づき、社員の能力を引き出すための評価制度の設計・運用、研修の企画、戦略的な人員配置、組織の風土づくりなどがこれにあたります。
求められる適性は、「戦略的思考」や「企画力」、そして経営と現場を繋ぐ「傾聴力」です。労務のように「守る」だけでも、採用のように「外に攻める」だけでもありません。会社の内側で「人を活かし、育てる」仕組みを作る、経営パートナーとしての役割です。
専任者が置けない場合、どう解決するか? 〜カギは経営者の「時間の強制確保」〜
役割の違いは分かった。しかし、多くの経営者の方がこう思われるはずです。
「年間数名の採用のために、3つの専門家なんて置けない」
その通りだと思います。それは非常に現実的で、正しい経営判断です。
ただ、ここで構造的な問題が起こります。 総務の方がすべてを兼務する場合、その担当者の方はもちろん真面目に、すべての業務に全力で取り組んでくださっています。しかし、「守り(労務)」は、ミスなく正確に行う堅実な思考が求められます。 「攻め(採用)」は、新しいアイデアを試す柔軟な思考や行動量・交渉術が求められます。
この正反対の思考モードを、一人の人間が一日の中で頻繁に切り替えるのは非常に困難です。 結果として、緊急性の高い「守り」の業務が優先され、「攻め」である採用活動はどうしても「思考が拡散」し、深く集中して取り組む時間が取れなくなってしまいます。現代の採用には、想像以上の時間と労力がかかります。
担当者の意欲の問題ではなく、「構造的に、攻めに集中できなくなっている」ことこそが、一番の問題です。この問題は、担当者の努力では解決できません。経営者の「決断」によってのみ解決できます。
重要なのは、「人」を専任で置くことではなく、「攻めの採用活動に”集中する”時間(工数)」を経営者が意図的に確保することです。
<変革案1:適任者が兼務する>
営業エースのBさんに、「営業 8割 + 採用 2割(”攻め”)」のミッションを与える。 ※社長が「君の営業時間の2割を採用活動に充ててほしい」と正式なミッションとして任命します。<変革案2:今の担当者の比率を変える>
総務担当Aさん(もし適性がある場合)の業務を見直し、「総務(守り) 6割 + 採用・人事(攻め) 4割」にする。 ※そのために、Aさんが行っていた他の業務を、社長が主導して他の社員に割り振るか、業務自体を「やめる」と決断します。
年間数名の採用だからこそ、その「1人」が会社の未来を大きく左右します。 だからこそ、「兼務」であっても、経営者が「集中できる時間」を強制的に作り出すことが、現実的な第一歩となります。
“分業”を”分断”にしない ~組織の戦略的連携~
さて、役割を分け、時間も確保した。しかし、これだけでは不十分です。 「労務担当は給与計算だけ」「採用担当は面接だけ」といったように、「分業」が「分断」になっては意味がありません。
「採用」「人事」「労務」は、すべて「人」という一本の軸で繋がっています。

よくある失敗は「穴の空いたザルの例え」です。 「採用」担当がどんなに頑張って新しい水(人材)を汲んできても、「労務」(働きにくい環境)や「人事」(育成しない・評価が不透明)が”ザル”であれば、人材は入社後すぐに流出してしまいます。
大切なのは、各担当者が得た情報を「連携」させ、経営判断に活かすことです。
例えば、 「労務」担当が、特定の社員の残業が急増していることに気づいたら、すぐに「人事」担当(または上司)に報告する。 「人事」担当はそれを受け、その社員と面談(1on1)を行い、業務負荷やメンタルの状況を確認し、手遅れになる前に対策を講じる。
このように、各機能が情報を持ち寄り、連携することで初めて「人を活かす」体制が機能します。 経営者や担当者が、これらの情報を横断で見て「会社全体の人事戦略」を考える”司令塔”としての視点を持つことが重要です。
📖 まとめ:「作業者」から「経営パートナー」へ。最初の一歩は”自社の棚卸し”から
「採用」「人事」「労務」は、もはや総務の「雑務」ではなく、企業の未来を左右する「専門業務」です。
限られたリソースの中で全てを完璧に行うことはできません。しかし、この記事でお伝えしたように、
●3つの役割(採用・人事・労務)と、それぞれに必要な「適性」を正しく理解すること。
●「専任が置けない」問題は、経営者の決断で「攻めの時間」を強制的に確保することで解決すること。
●適性のある人に(たとえ兼務でも)そのミッションを任命すること。
●そして最も重要なのは、それらの担当者が情報を「連携」させ、経営戦略に活かす視点を持つこと。
これらは、今日からでも意識改革として始められることです。 総務担当者も、これからは単なる「作業者」から、人を活かす戦略を考える「経営パートナー」へと意識をアップデートする時が来ています。
まずは、あなたの会社の「人事機能」を、この3つの視点で棚卸しすることから始めてみてはいかがでしょうか。
📚参考:地方企業の採用参考企業は?
- 株式会社和郷( https://www.wagoen.com/recruit/ ) / 千葉県香取市
採用サイト(リクルーティングサイト)が整備されており、「人」「数字」「事業」「デザイン」と幅広い分野で視覚的にも、感情的にも魅力付けが上手です。 - 株式会社Hinotori( https://hinotori-trip.com/corporate/about/ ) / 福島県会津若松市
創業間もないスタートアップ企業。代表の経験(マーケター)を活かした企業ブランディング、SNSでの発信、戦略立ては非常に秀逸です。 - 小湊鐵道株式会社 (https://www.kominato.co.jp/ ) / 千葉県市原市
創立100年の里おこしベンチャー、逆開発、など独自性のある強みを全面に打ち出し多角的な経営を行う市原地域を代表する企業です。直近2年間で採用数が3倍増加中です。
私たちは、地方の中堅中小企業の「採用が変わる」お手伝いをしています。
「うちの場合、具体的にどうすれば?」と悩んだら、ぜひお気軽にご相談ください。
御社の採用活動方法や現在のお悩みをお聞かせいただきながら、
解決策や具体的な手法をご提案させていただきます。
まずはお悩み相談から、お気軽にお問い合わせください。

